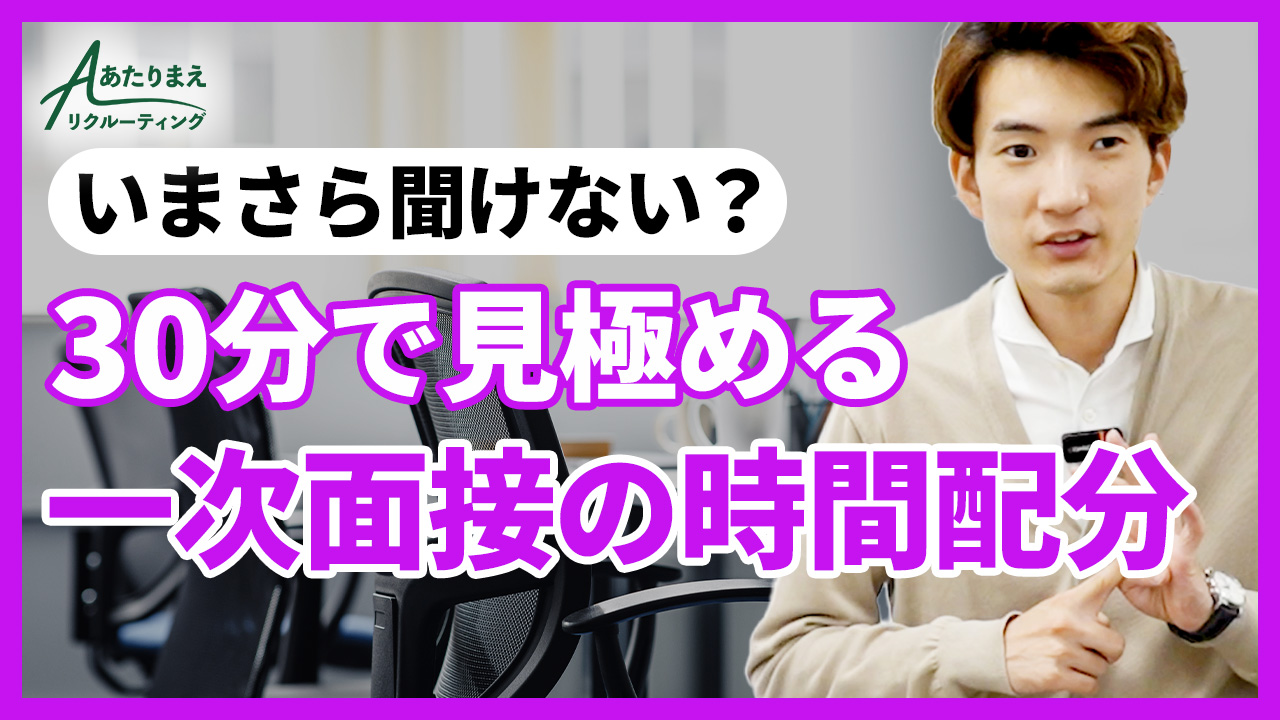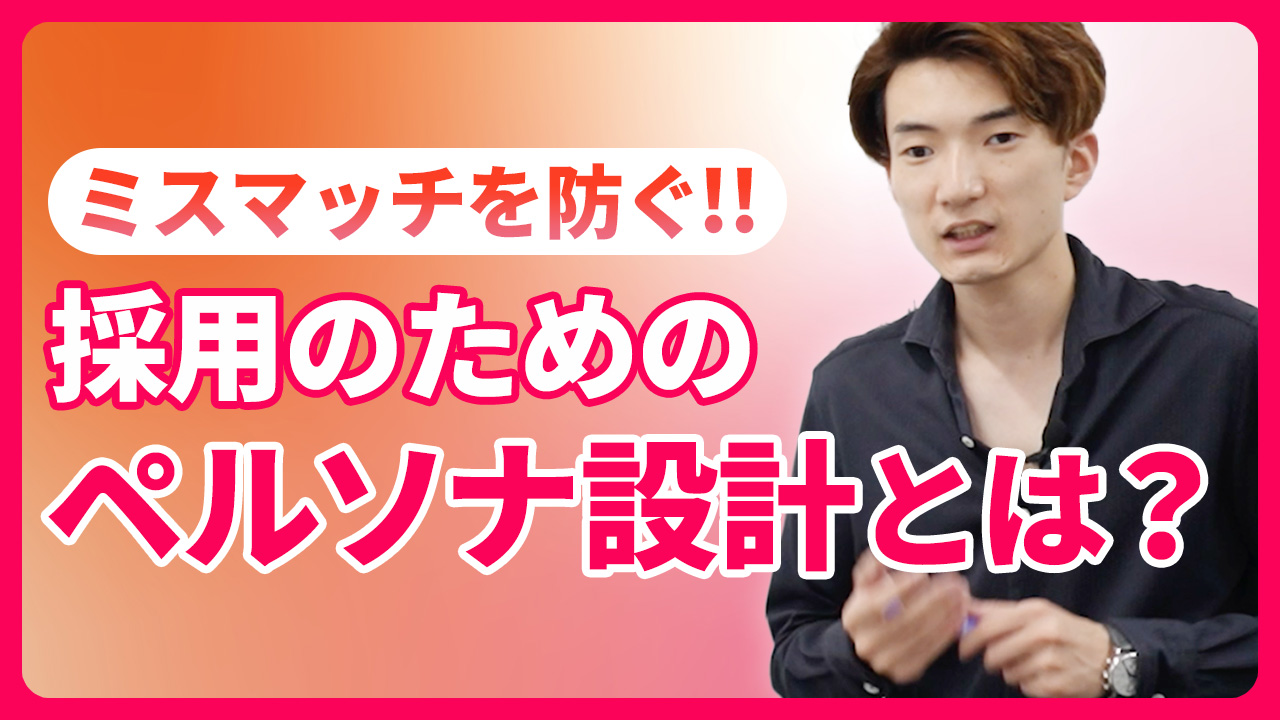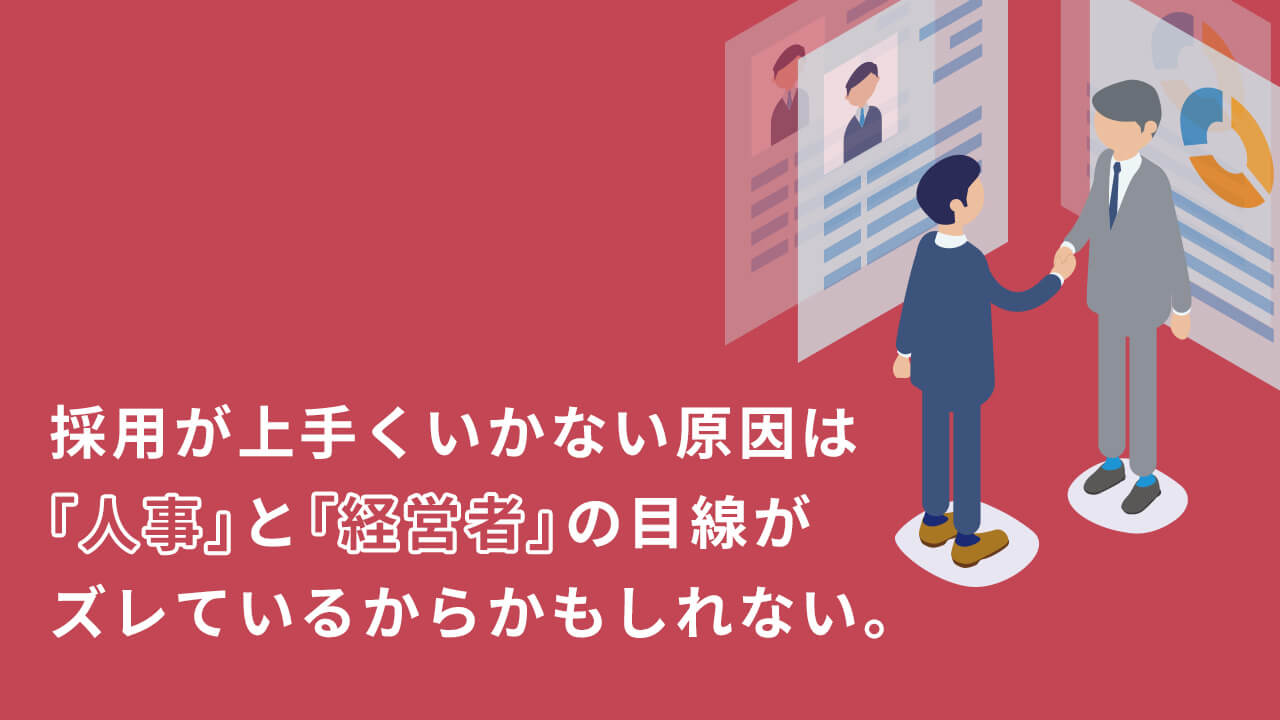
「採用予算は確保した、人事担当者もいる、求人も出している。なのになぜ採用がうまくいかないのか?」
「採用支援会社に依頼したのに、思うような結果が出ない。採用支援って意味ないのでは?」
このような悩みを抱える企業は少なくありません。採用手法やツールにばかり目が向きがちですが、実は根本的な問題は別のところにあるかもしれません。
それは、組織内の目線のズレです。特に経営者、人事、現場という3つの異なる立場が、それぞれ異なる視点で採用を捉えていることが、採用失敗の真の原因となっているケースが多いのです。
また、多くの採用支援会社が「必ず採用します」と安易にコミットすることで、却って問題を複雑化させているケースも見受けられます。
本記事では、採用がうまくいかない根本原因と、その解決策について、あたりまえリクルーティングの視点から解説します。
監修者

株式会社Revive代表
熊野拓人
法人向けにインフラ系商材の電話営業を行い、キャリア内で全国売上No.1の販売代理店において新人賞を3ヶ月で獲得。営業人材の育成、営業業務の代行を主軸に2021年株式会社Reviveを設立。2年で計100名以上の営業組織を構築し、50社以上の営業プロジェクトに携わる。後に動画やWebにおけるクリエイティブの制作から採用支援サービスを開始。現在では採用計画の立案から、一次面接の代行までを請け負う総合的な採用支援活動を行い、中小企業を中心に約50社以上を採用成功に導く。

株式会社Revive代表
熊野拓人
法人向けにインフラ系商材の電話営業を行い、キャリア内で全国売上No.1の販売代理店において新人賞を3ヶ月で獲得。営業人材の育成、営業業務の代行を主軸に2021年株式会社Reviveを設立。2年で計100名以上の営業組織を構築し、50社以上の営業プロジェクトに携わる。後に動画やWebにおけるクリエイティブの制作から採用支援サービスを開始。現在では採用計画の立案から、一次面接の代行までを請け負う総合的な採用支援活動を行い、中小企業を中心に約50社以上を採用成功に導く。
目次
採用における3つの視点:経営者、人事、現場の役割と目標
経営者の視点:事業計画ベースの「計画」
経営者は事業計画に基づいて採用計画を立てます。ここで重要なのは、これは「戦略」ではなく「計画」だということです。
経営者が見ているもの
- PL(損益計算書)への影響
- 事業成長に必要な人員数
- 投資対効果(ROI)
- 中長期的な事業戦略
経営者の採用に対する考え方
- 「今期の売上目標達成のため、営業を5名採用する」
- 「新規事業のため、エンジニアを3名、来年度までに確保したい」
- 「予算は年間500万円以内で」
経営者にとって採用は、事業計画を実現するための手段であり、最終的な成功指標は「採用した人材が実際に活躍し、事業に貢献したか」です。
人事の視点:計画を実現するための「戦略」
人事は、経営者が立てた計画に基づいて、具体的な採用戦略を立案・実行します。
人事が見ているもの
- 採用目標人数の達成
- 予算内での効率的な採用活動
- 採用プロセスの最適化
- 候補者の質と量のバランス
人事の採用に対する考え方
- 「営業5名を予算内で採用するため、どの媒体を使うか」
- 「面接プロセスをどう設計するか」
- 「内定辞退を防ぐにはどうすればよいか」
人事にとって採用は、与えられた目標を達成するためのプロジェクトであり、成功指標は「予算内で予定人数を採用できたか」となります。
現場の視点:即戦力としての「実用性」
現場(営業、エンジニア、製造など)は、自分たちの業務目標達成の観点から採用を捉えます。
現場が見ているもの
- 自部署の業務目標達成
- 即戦力となる人材の確保
- チームとの相性
- 現実的な業務遂行能力
現場の採用に対する考え方
- 「売上目標達成のため、すぐに戦力になる人が欲しい」
- 「技術的に高いレベルの人材を採用してほしい」
- 「チームワークを重視する人を求めている」
現場にとって採用は、自分たちの目標達成を支援してくれる仲間探しであり、成功指標は「採用された人材がすぐに戦力になるか」です。
経営者と人事の解像度の違い
ここで重要なのは、経営者と人事では見ている解像度が全く異なるということです。
経営者の解像度
- 全体最適の視点
- 結果重視(採用した人が活躍したか否か)
- 中長期的な事業インパクト
人事の解像度
- 部分最適の視点
- プロセス重視(採用目標人数の達成)
- 短期的な採用完了
この解像度の違いが、様々な問題を引き起こします。
よくあるズレのパターン
ケース1:予算に対する考え方
- 経営者:「500万円投資して、1億円の売上を作る人材を採用したい」
- 人事:「500万円の予算で5名採用しなければならない」
ケース2:採用基準
- 経営者:「多少時間がかかっても、質の高い人材を採用したい」
- 人事:「期限までに必要人数を確保しなければならない」
ケース3:成果の測定
- 経営者:「採用した人材の業績貢献度で判断したい」
- 人事:「予定通り採用できたかで判断している」
現場を加えた3者の複雑な関係
さらに複雑なのは、ここに現場の視点が加わることです。
3つの組織の求めるもの
経営者:事業成長への貢献
人事:採用プロセスの完遂
現場:即戦力の確保
この3つの要求が必ずしも一致しないところに、採用の難しさがあります。
現場が加わることで生じる新たなズレ
現場 vs 経営者
- 現場:「今すぐ戦力になる人が欲しい」
- 経営者:「将来性を重視した採用をしたい」
現場 vs 人事
- 現場:「技術レベルの高い人材を採用してほしい」
- 人事:「予算の関係で、もう少し条件を下げてもらえませんか」
現場内での対立
- 営業部:「営業経験者を優先してほしい」
- 技術部:「エンジニアの採用を急いでほしい」
目線のズレが生む採用失敗のメカニズム
悪循環のパターン
- 計画と実行のズレ
- 経営者の計画が現実的でない
- 人事が実現可能な戦略に落とし込めない
- コミュニケーション不足
- 各部署が自分の視点でしか物事を見ない
- 相手の立場や制約を理解しない
- 責任の押し付け合い
- 経営者:「なんで採用できないんだ!」
- 人事:「予算が足りません、条件が厳しすぎます」
- 現場:「使えない人ばかり採用される」
- 組織の焦げ付き
- 部署間の信頼関係悪化
- ギスギスした組織風土
- 採用活動の停滞
焦げ付いた組織の特徴
経営者の不満
- 「投資した採用予算に見合う成果が出ない」
- 「人事部は何をやっているのか分からない」
- 「現場のわがままに振り回されている」
人事の不満
- 「無理な要求ばかりされる」
- 「予算も人手も足りない」
- 「誰からも評価されない」
現場の不満
- 「求めている人材が採用されない」
- 「採用された人がすぐに辞めてしまう」
- 「人事部は現場のことを分かっていない」
解決の鍵:適切なコミュニケーションと相互理解
重要なのは「誰が悪い」ではない
この問題を解決するために重要なのは、「誰が悪い」という犯人探しではありません。経営者、人事、現場それぞれに正当な理由と制約があり、それぞれの視点で最善を尽くしているのです。
問題は、それぞれの役割と視点の違いを理解した上で、適切なコミュニケーションが取れていないことにあります。
人事に求められる「翻訳者」としての役割
理想的には、人事が3つの組織の橋渡し役として機能すべきです。
人事の本来の役割
- 経営者の事業計画を現実的な採用戦略に翻訳する
- 現場の要求を経営者に適切に伝える
- 3者の利害を調整し、全体最適を図る
具体的なコミュニケーション例
経営者に対して:
「売上1億円の人材を採用するには、市場価値として年収600万円程度が必要です。予算500万円では、育成前提での採用になります」
現場に対して:
「即戦力採用をご希望ですが、今の予算と条件では、ポテンシャル採用で育成していく方針になります」
経営者と現場の調整:
「現場は即戦力を求めていますが、将来性重視の経営方針とのバランスを取る必要があります」
しかし、現実は難しい
ただし、この「翻訳者」としての役割を完璧にこなすには、非常に高度なスキルが必要です:
- 事業理解力
- 市場知識
- 交渉力
- 調整力
- 戦略思考
まさに「こんなの出来てたら自分で会社やってる」レベルの能力が求められるのです。
外部パートナーという「潤滑油」の必要性
餅は餅屋:専門家に任せる意義
採用が組織という歯車だとすれば、経営者、人事、現場はそれぞれ重要な歯車です。しかし、歯車だけでは回りません。適切な潤滑油が必要なのです。
この潤滑油の役割を果たすのが、外部の採用専門パートナーです。
潤滑油に求められる核心的要件:二軸思考
優秀な採用パートナーに求められるのは、二軸での思考能力です。
軸1:経営者の意図理解
- なぜその採用が必要なのか?
- 事業戦略上の位置づけは?
- 投資対効果への期待値は?
軸2:現場の現実性
- 実際にその条件で採用可能なのか?
- 市場の実態はどうなっているのか?
- 競合他社の動向は?
この両軸をしっかりと把握した上で、現実的な落とし所を提案するのが真のプロフェッショナルです。
どちらか一方だけでは機能しません。経営者の理想だけを聞いて「頑張ります!」では無責任ですし、現場の現実だけを見て「無理です」では価値がありません。
本来の採用支援:三角関係でのコミュニケーション
多くの企業で間違えているのが、採用支援会社とのコミュニケーション構造です。
よくある間違ったパターン:
経営者 → 人事 → 採用支援会社
この場合、情報が伝言ゲーム化し、経営者の真意が採用支援会社に伝わりません。
あるべき正しいパターン:
採用支援会社
/ \
経営者 ↔︎ 人事 ↔︎ 現場
人事は「新しく使える駒」ではありません。重要なステークホルダーの一人として、経営者と対等にコミュニケーションを取る必要があります。
外部パートナーだからこその価値
しがらみのない客観性
社内の人間関係や政治に巻き込まれることなく、純粋にデータと事実に基づいて判断できます。
遠慮のない本音のコミュニケーション
外部の人間だからこそ、社内では言えない本音を伝えることができます。
経営者に対して:
「申し訳ございませんが、この採用計画、現在の市場では実現不可能です。予算を2倍にするか、条件を見直すか、どちらかしかありません」
人事に対して:
「すみません、この採用手法、効率が悪すぎます。昭和の手法ですね。もっと戦略的にアプローチしましょう」
現場に対して:
「その要求、ちょっとわがままが過ぎませんか?市場を理解してください。理想と現実は違います」
専門的な知識と経験
- 業界の採用トレンド
- 効果的な採用手法
- 適正な採用コスト
- 成功事例と失敗事例
中立的な調整役
- 各部署の要求を客観的に整理
- 全体最適な解決策の提案
- 建設的な議論のファシリテート
外部パートナーがいない場合の「焦げ付き」
潤滑油がない歯車は、やがて焦げ付きます。採用組織も同様です。
想像してみてください。車のエンジンオイルを交換せずに走り続けたらどうなるでしょうか?最初はなんとか動きますが、やがて摩擦が増し、熱を持ち、最終的にはエンジンが焼き付いて完全に停止してしまいます。
典型的な焦げ付きパターン
- 経営者:「人事は何をやっているんだ!数字が読めないのか!」
- 人事:「無理な要求ばかりして…現場も分かってくれない…」
- 現場:「また使えない人を採用してきた…人事は現場のことを何も分かっていない」
結果として起こること
- 部署間の信頼関係悪化
- 採用活動の停滞
- 組織全体のモチベーション低下
- 優秀な既存社員の離職(こうなったら本末転倒です)
あたりまえリクルーティングが果たす「潤滑油」の役割
3者の橋渡しとしての機能
あたりまえリクルーティングは、経営者、人事、現場の3者をつなぐ潤滑油として機能します。
経営者との関係
- 事業計画の理解と採用戦略への翻訳
- 現実的な採用可能性の提示(時には厳しい現実も)
- ROIに基づいた採用提案
人事との関係
- 採用戦略の共同立案
- 実務レベルでの効率化支援
- 専門知識の提供とスキル向上支援
現場との関係
- 現場ニーズの詳細ヒアリング
- 現実的な採用可能性の説明(時には諦めてもらうことも)
- 採用した人材の活躍支援
「嫌われ役」を引き受ける価値
外部パートナーの重要な役割の一つが、「嫌われ役」を引き受けることです。
これは冗談ではありません。社内の人間では言いにくい厳しい現実を、外部だからこそ遠慮なく伝えることができます:
- 「申し訳ありませんが、この条件では求める人材は絶対に採用できません」
- 「現在の採用手法、完全に時代遅れです。今すぐ変えましょう」
- 「予算と要求が全く見合っていません。どちらかを変えてください」
まるで、健康診断で「このままだと死にますよ」とハッキリ言ってくれる医者のような存在です。聞きたくない現実かもしれませんが、必要な情報なのです。
これにより、社内の人間関係を悪化させることなく、必要な軌道修正を行うことができます。
実際の調整事例
ケース:IT企業でのエンジニア採用
状況:
- 経営者:「年収400万円でシニアエンジニア3名、3ヶ月で採用してくれ」
- 人事:「予算が厳しく、応募が全然集まりません…」
- 現場:「即戦力のシニアエンジニアじゃないと困る」
あたりまえリクルーティングの調整:
経営者に対して:
「申し訳ございませんが、年収400万円でシニアエンジニアの採用は、宝くじに当たるレベルで困難です。選択肢は3つです:
- 予算を600万円に上げてシニア採用(現実的)
- 400万円でジュニア採用し、育成投資(時間はかかるが確実)
- 採用期間を1年に延長して奇跡を待つ(おすすめしません)」
現場に対して:
「即戦力をご希望ですが、予算制約があります。正直に申し上げて、その条件では無理です。ジュニアエンジニアを採用し、現場で育成していただく前提で進めませんか?その代わり、育成しやすい素養とやる気のある人材を厳選します」
結果:
経営者が現実を理解し育成投資の必要性を受け入れ、現場が育成の協力を約束。予算は450万円に調整され、ポテンシャルの高いジュニアエンジニア3名の採用に成功。
半年後、そのうち2名が戦力として活躍中。1名は他社に転職しましたが、「これも想定の範囲内」として、継続的な採用活動を実施しています。
結果にコミットしない誠実さ:あたりまえリクルーティングの哲学
採用支援のコミットの真実
多くの採用支援会社が「必ず採用できます!」「結果にコミットします!」と謳っていますが、これらの約束に疑問を感じたことはありませんか?
採用支援 コミットというキーワードで検索すると、数多くの会社が結果保証を謳っています。しかし、本当にそれは可能なのでしょうか?
「採用支援が意味ない」と言われる理由
「採用支援を使ったけど全然採用できなかった。採用支援って意味ないのでは?」
このような声をよく聞きます。では、なぜ「採用支援が意味ない」と感じる企業が多いのでしょうか?
主な理由:
- 現実的でないコミットメント:「必ず採用します」という約束
- 運要素の無視:採用の成功確率を100%だと錯覚させる
- 条件と現実のギャップ:市場価値を無視した条件設定
- 短期的な結果のみを評価:プロセスの価値を理解しない
実は、「採用支援が意味ない」のではなく、間違った期待値設定と非現実的なコミットメントが問題なのです。
「採用できるorできないは知らん」という正直さ
ここで、多くの採用支援会社とは異なる、あたりまえリクルーティングの重要な考え方をお伝えします。
率直に言います:
採用できるかどうかは運要素もあるので、正直分かりません。
これは無責任な発言ではありません。むしろ、最も誠実で現実的な姿勢です。
ただし、もし本当に結果にコミットしろと言うなら、できますよ?
条件があります:
- 年収を今より200万円上げてください
- オフィスを一等地のガラス張りビルに移転してください
- 社長を絶世の美女に変えてください
- ついでに副業OKで、リモートワーク完全自由にしてください
え?「それは無理だ」ですって?
そうです、無理でしょ(笑)
つまり、現在の条件のまま「必ず採用します」というのは、上記と同じレベルで非現実的な約束なのです。
なぜ「採用支援 コミット」は危険なのか
採用支援会社が安易に結果にコミットすることの問題点を整理してみましょう。
理由1:
運要素が確実に存在する 採用には、どんなに優秀な戦略を立てても避けられない運要素があります:
- 候補者の転職タイミング
- 競合他社の動き
- 経済情勢の変化
- 候補者の個人的事情
これらをコントロールすることは、天気をコントロールするのと同じくらい困難です。
理由2:
N1(1件)の結果で判断するのはナンセンス 「1名採用できなかった = 採用支援が失敗」という判断は統計的に意味がありません。まるで、「今日雨が降ったから天気予報は外れた」と言っているようなものです。
理由3:
コントロールできないものにコミットするのは詐欺 「必ず採用します!」と約束する採用支援会社は、正直に言って詐欺に近いと思います。市場条件、候補者の状況、競合の動きなど、コントロールできない要素があまりにも多いからです。
本当の「採用支援の意味」とは
「採用支援 意味ない」と感じる企業に、真の採用支援の価値をお伝えします。
採用支援の本当の意味は、結果の保証ではなく「前に進むこと」です。
あたりまえリクルーティングがコミットするのは「プロセスの質」
具体的には:
- あらゆる手法を検討する
- 現状条件での最適解を提示する
- ベストと思われる戦略を実行する
- 結果に関わらず、次の打ち手を用意する
- データに基づいた改善提案を継続する
「採用できませんでした」も価値ある情報
多くの人が誤解していますが、「採用できませんでした」という結果も、実は非常に価値のある情報です。
なぜなら、「なぜ採用できなかったのか」を正確に分析し、次の戦略に活かすことができるからです。
例: 「年収400万円の条件では、3ヶ月間で応募者5名、面接実施3名、内定辞退2名、最終的に採用0名でした。市場調査の結果、同職種の相場は550万円です。次のアプローチとしては…」
この情報があることで、次回はより現実的な戦略を立てることができます。
これこそが、本当の意味での「採用支援」なのです。甘い約束ではなく、現実的な価値提供。
運要素を認めつつ、確率を上げる
採用に運要素があることを認めた上で、私たちができるのは成功確率を上げることです。
まるで、プロのポーカープレイヤーのように。彼らも「必ず勝つ」とは言いませんが、長期的に勝率を上げる戦略を持っています。
確率を上げる具体的な方法:
- より多くの候補者と接触する
- 魅力的な求人内容に改善する
- 効率的な選考プロセスを設計する
- 内定辞退を防ぐフォローを強化する
- 継続的にデータを分析し、戦略を改善する
医者だって「必ず治します」とは言いません。「最善の治療を行います」と言うのです。
採用も同じです。最善の戦略を立て、最高のプロセスで実行し、結果を分析して次に活かす。これこそが、私たちの掲げているサービスの価値なのです。
まとめ:採用成功のための「全体最適」の視点
採用がうまくいかない真の原因
採用がうまくいかない理由は、採用手法やツールの問題ではなく、組織内の目線のズレと適切なコミュニケーション不足にあることが多いのです。
経営者、人事、現場という3つの歯車が、それぞれ異なる方向を向いて回っていては、採用という機械は正常に機能しません。
解決のためのポイント
- それぞれの役割と視点を理解する
- 経営者:事業計画と全体最適
- 人事:戦略実行と効率化
- 現場:実用性と即戦力
- 適切なコミュニケーションを心がける
- 相手の立場を理解した上での要求
- 現実的な制約の共有
- 建設的な議論と妥協点の模索
- 外部の専門家を活用する
- 客観的な視点での問題整理
- 遠慮のない現実的な提案
- 専門知識に基づく戦略立案
あたりまえリクルーティングからのメッセージ
採用は組織の成長を支える重要な活動です。しかし、その成功は採用手法だけでなく、組織内の連携と適切なコミュニケーションにかかっています。
私たちあたりまえリクルーティングは、経営者、人事、現場をつなぐ潤滑油として、組織全体の採用力向上をサポートします。
「誰が悪い」ではなく「どうすれば良くなるか」
この視点で、一緒に採用成功を実現しませんか?
採用がうまくいかない理由が組織内の目線のズレにあることをご理解いただけたと思います。しかし、この問題の解決には専門的な知識と中立的な立場が必要です。
こんなお悩みはありませんか?
- 経営者と現場の要求が全く合わない
- 採用予算と求める人材レベルが見合っていない
- 部署間で採用に対する温度差がある
- 誰が何をすべきか分からない状態が続いている
あたりまえリクルーティングでは、このような組織内の調整と採用戦略の両方をサポートしています。
外部の潤滑油として、組織の歯車を滑らかに回しながら、採用成功を実現します。
まずは組織の現状分析から始めてみませんか? 貴社の採用における目線のズレを客観的に分析し、具体的な解決策を無料でご提案いたします。